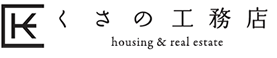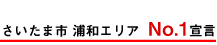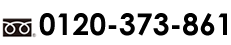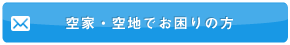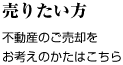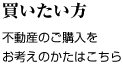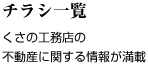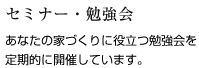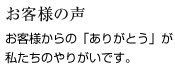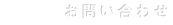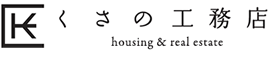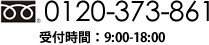スタッフブログ:月別: 2022年8月
首都圏直下地震
2022年08月31日
さいたま市での不動産の売却・購入から居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

東京など首都圏を襲う「首都直下地震」。東京都は、首都直下地震の被害想定を10年ぶりに見直しましたと報道されましたが想定したのは、首都機能や交通網に大きな影響を及ぼす「都心南部直下地震」のほか、島しょ部への津波の影響が大きい南海トラフの巨大地震など、8つの地震です。
最も大きな被害が想定されたのは冬の午後6時に、風速8メートルのなか、「都心南部直下地震」がマグニチュード7.3で起きた場合です。
江東区や江戸川区など11の区の一部で震度7の揺れを観測し、23区のおよそ6割では震度6強以上になるとしています。
また、全壊する建物はおよそ8万2200棟に上るとの予想です。
東京の被害想定は10年前よりは少なくなっているようですが被害想定が小さくなったことについては、いまの耐震基準に基づいた住宅が増えて9割以上になったことや、木造住宅が密集する地域が半減したことなどが理由だとしています。
詳しくは下記をご参照ください。
私が住んでいる埼玉も調べてみました。
首都直下地震+埼玉県で検索しますと埼玉県の震災対策のページが表示されました。
埼玉県のHPには埼玉県地震被害想定調査被害分布図の表示というページがありそこには
想定地震に対して震度分布図・液状化可能性分布図・建物全壊棟数分布図・火災消失棟数分布図があり表示することができます。
まずは、お住まいの地域の現状を把握してみてはいかがでしょうか。
詳しくは下記をご参照ください。
埼玉県地震被害想定調査被害分布図
http://bousai.pref.saitama.lg.jp/menu.html
これからお住まいを探す際は探している市町村のHPから色々な情報を集めその中でもハザードマップは必ずご確認頂き候補地を検討されてはいかがでしょうか。
まずは災害に強い家をご検討ください。
~人生に愛すべき住まいを~
さいたま市の不動産の売却・購入は、くさの工務店にご相談ください。
権利証を紛失してしまったら その1
2022年08月30日
さいたま市での不動産の売却・購入から居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。
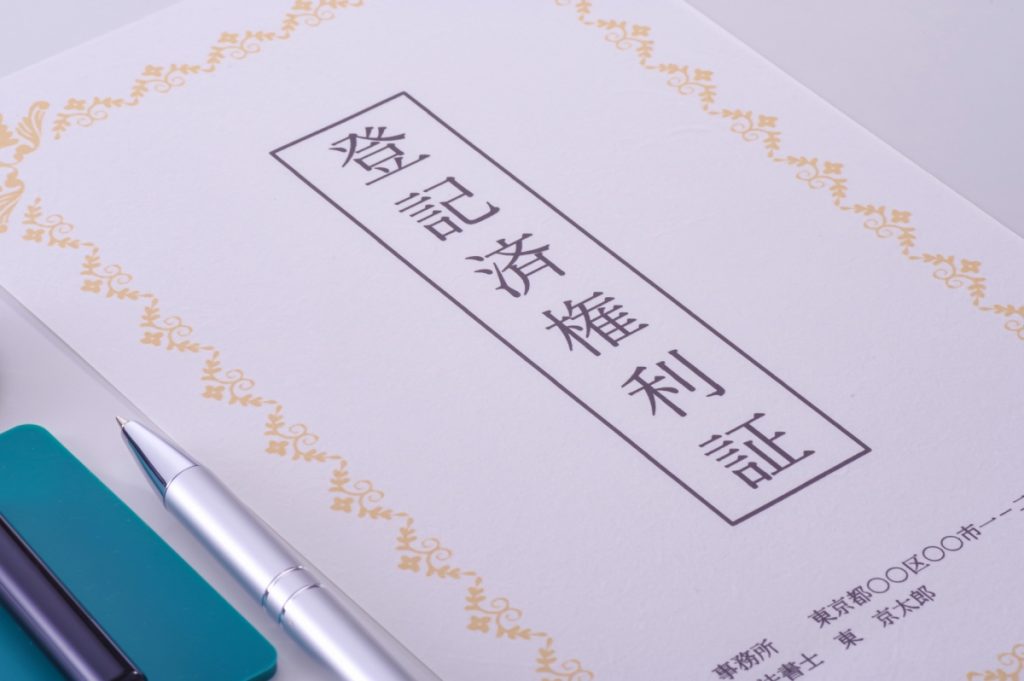
不動産を購入した場合には、新たに権利証が発行されます。
正式には、「登記識別情報」と呼ばれる、不動産の取得者ごとに通知されるパスワードがその不動産の所有者である証明となります。
そしてそのパスワードの通知書が「登記識別情報通知」と呼ばれる、いわば権利証なのです。
権利証は再発行ができない
この権利証は、再発行の制度がありません。
仮に紛失してしまった、盗難にあった、毀損してしまった、といった場合でも、再発行はできません。
中には銀行の貸金庫に保管をしている方もおりますが、大切に保管することが必要です。
権利証がない場合の手続き
権利証を使う場面としては、その不動産を売却する場合や、住宅ローンを借りる手続きをする場合です。
それらの場合に権利証を紛失してしまっているときは、権利証の提出に代わる手続きをすることになります。
①事前通知制度
ひとつめは、法務局の事前通知制度を利用する方法です。
これは、権利証が必要な登記の手続きを法務局へ申請した際に、権利証がないことを伝えると、後日法務局から本人宛に「本人限定郵便」で、「登記申請がされていますけど間違いありませんか」という趣旨の照会書が届きます。
こちらの書類に返信することで、登記の手続きがきちんと処理される、という方法です。
ところがこの方法は、不動産の売買の場面では使うことができません。
不動産の取引においては、売買代金の支払いと権利の引渡しは同時である必要があります。
買主が先に全額を支払ったのに、仮に売主がこの回答書を無視した場合には、権利が引き渡されないこととなってしまいます。
②公証人の認証
ふたつめは、公証役場にて、登記の書類に認証をもらう、という方法です。
例えば売買においては、公証人が売主の意思確認・本人確認を行うことで、権利証がなくても登記手続きを進めても問題ない、というお墨付きを与えるという方法です。
ただ、売買の実務においてもこの方法が採用されるケースは少ないため、公証人自体もこの制度に不慣れでいることが実情です。
③司法書士による本人確認
最後が、司法書士による本人確認・意思確認を行い、登記の手続きを進める方法です。
不動産の取引にも明るく、登記手続きのスペシャリストである司法書士に任せることで、権利証を紛失している場合でも手続きがスムーズに進むことになります。
取引の場でメジャーな方法はこの三番目になります。
ただ、コストがかかってしまう点がネックとなります。
以上のように、権利証を紛失した場合でも、手続ができないことはないのですが、手間や費用がかかってしまいます。
やはり一番肝要なのは、権利証を大切に保管し、紛失しないことかと思います。
~人生に愛すべき住まいを~
さいたま市の不動産の売却・購入は、くさの工務店にご相談ください。
2022年7月度の不動産相場
2022年08月28日
さいたま市での不動産の売却・購入から居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

■成約平米単価の前年同月比(2022年7月)
成約平米単価はすべて地域が前年比で上昇続く
公益財団法人東日本不動産流通機構(通称:東日本レインズ)から、2022 年7月度の不動産流通市場動向が発表されました。以下、首都圏エリアの中古マンション地域別成約平米単価の部分を抜粋しました。詳細は下記リンクをご覧ください。
○東京都
7 月の東京都区部は 99.81 万円/㎡で前年比プラス 11.3%の 2 ケタ上昇となり、20 年 5 月から 27 ヶ月連続で前年同月を上回った。多摩は 49.67 万円/㎡と前年比で 7.4%上昇し、21 年 3 月から 17 ヶ月連続で前年同月を上回った。
○神奈川県
7 月の横浜・川崎市は 56.67 万円/㎡と前年比で 3.2%上昇し、20 年 6 月から 26 ヶ月連続で前年同月を上回った。神奈川県他は 38.94 万円/㎡で前年比プラス 18.9%の 2 ケタ上昇となり、20 年 12 月から 20ヶ月連続で前年同月を上回った。
○埼玉県・千葉県
7 月の埼玉県は 41.66 万円/㎡で前年比プラス 19.8%の 2 ケタ上昇となり、20 年 6 月から 26 ヶ月連続で前年同月を上回った。千葉県は 35.51 万円/㎡で前年比プラス 13.3%の 2 ケタ上昇となり、20 年 8 月から 24 ヶ月連続で前年同月を上回った。
◆公益財団法人東日本不動産流通機構
『月例報告 Market Watch サマリーレポート 2022年7月度』
http://www.reins.or.jp/pdf/trend/mw/mw_202207_summary.pdf
家を持っている方も、これから買う方も、常に不動産相場は確認しておくようにしましょう!
~人生に愛すべき住まいを~
さいたま市の不動産の売却・購入は、くさの工務店にご相談ください。
能登地方の最大震度6弱の地震から学ぶ ~ 住宅購入のポイント ~
2022年08月27日
さいたま市での不動産の売却・購入から居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

■春先から日本周辺で頻発する地震情報について
石川県の能登地方で6月19日に最大震度6弱の地震が発生しました。この地震を踏まえ、政府の地震調査委員会(委員長・平田直東京大名誉教授)は6月20日、文部科学省で臨時会合を開き、長期化地震につながる懸念を発表しました。
その予兆として、春先から日本周辺で震度3~4程度の地震が頻発していました。3月以降、これまでに最大震度4以上は全国で計23回を数え、今回の地震を含めると26回となりました。1~2月の計3回から大幅に増えており、5月29日も茨城県沖を震源に震度4が観測されたばかりでした。気象庁の発表によると地震活動は活発な時期と落ち着いた時期がある事を発表されていますが、日ごろの備えは欠かせない事が改めて実感できます。これから不動産購入をされる方は、改めて地震大国日本という事を頭の片隅において欲しいと思います。
<3月以降の、最大震度4以上の地震(全国で合計26回発生)>
日高地方東部:震度4(1回発生)
岩手県沖:震度4(1回発生)、震度5強(1回発生)
福島県沖:震度4(1回発生)、震度5弱(1回発生)、震度6強(1回)
茨城県沖:震度4(1回発生)、震度5弱(1回発生)
茨城県北部:震度4(1回発生)、震度5弱(1回発生)
茨城県南部:震度4(1回発生)
東京湾:震度4(1回発生)
愛知県東部:震度4(1回発生)
能登地方:震度4(3回発生)、震度5強(1回発生)、震度6弱(1回発生)
能登半島沖:震度4(2回発生)
京都府南部:震度4(2回発生)
和歌山県北部:震度4(1回発生)
※上記地震の発生回数は2022年6月21日現在のものとなります。
■2018年以降、地震の活動期となり、そのようなタイミングで住宅購入をされる方へ
3月以降、震度4を4回観測した石川県の能登半島は6月19日に発生した地震の予兆があった事になります。2018年ごろから地震は増加傾向で、2020年12月からはさらに活発な状況が続いています。この能登半島に火山はなく、群発地震が起きやすいとされる場所ではありませんが、地下で活動する高圧の熱水が要因との指摘もあるが、明確なメカニズムはわかっていないようです。
■首都圏で住宅購入を検討される方へ 人生の1/3の時間を自宅で過ごす事を考える!
首都圏では3月以降、最大震度4や5弱の地震が続いております。首都圏の地下は、陸の北米プレートの下に海の太平洋プレートとフィリピン海プレートが沈み込む複雑な構造で、もともと地震が多発する場所です。その為、これから住宅購入をされる方には、住宅の耐震性についても考慮していただきたいと思います。2021年10月に首都圏で5強を観測した地震は千葉県北西部が震源で、過去にも同規模の地震が繰り返し起きています。
また日本政府は、M7クラスの首都直下地震が今後30年以内に70%の確率で起きると発表しておりますので、これから住宅購入をされる方は、この規模の地震を経験する可能性がある事を強く認識しておいて欲しいと思います。
死者が最大32万人に上ると想定される南海トラフ地震については、かなりの備えが必要だと思いますが、人生の1/3の時間を自宅で過ごす事を考えると、このような地震が多い時期に住宅購入をされる方は、耐震性の重要性を考慮して、ご自宅探しをしていただきたいと思います。現在、不動産価格が高騰し、建築単価も上がっています。ついつい地震に対する備えを見落としがちですので、常に日頃の備えの大切にしていただきたいと思います。
今後の参考にお役立て下さい。
~人生に愛すべき住まいを。~
さいたま市の不動産の売却・購入は、くさの工務店にご相談ください。
戸建てに似ているけど違う「テラスハウス」とは?
2022年08月25日
さいたま市での不動産の売却・購入から居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

戸建ての物件を探していたら、周辺価格と比較してもかなり安い。
でも、事故物件でも借地権の物件でもない!これはなんでこんなに安いの?と疑問に感じたことは無いでしょうか。
これは、テラスハウス(連棟式住宅)の可能性が高いので、売却物件情報が掲載されているページに外観写真があったらまず外観を確認をしてください。
テラスハウスとは?
一戸建ての佇まいと似ている家屋のテラスハウス。不動産用語では、長屋住宅、連棟住宅とも呼ばれています。
同じような建物で、テラスハウスとは別にタウンハウスという家屋も存在しています。
住宅の種類は一戸建てかマンションかの2択しかないと思われがちなのですが、テラスハウスやタウンハウスも予算や地域、家族構成によってはお得に買える物件かもしれません。
しかし、メリットやデメリット、またテーマにもあるように住宅ローンについて学習をしておくべきことも必要なので、今回の記事ではテラスハウスの購入について簡単にお伝えします。
一戸建てとの違いは?
一戸建てとテラスハウスは非常に似ている物件です。
建物自体の違いをまずは理解しておきましょう。
一番の違いは、隣家が壁で繋がっていることです。
お隣と土地で分かれている一戸建てとは違い、壁一枚で仕切られている住宅をテラスハウスと呼びます。
一戸建て住宅は、一つの敷地に位置住宅であるのに対し、テラスハウスは、一つの敷地に対して境界壁を共有して複数の住戸が連続してある建物。
アパートやマンションとの大きな違いは、住戸に直接出入りできること。
建物全体の出入り口(エントランス)や廊下・階段・エレベーター等を他の住人と共有しない造りになっています。
また、同じような形状でタウンハウスという物件種類もありますが、テラスハウスと同様、連棟住宅となり、最大の違いは、タウンハウスは土地を共有、テラスハウスは土地まで分割されている為、個人の所有となります。
テラスハウスの特徴
隣家と壁を共有することで単純に外壁の面積が少なくなるうえ、電気・ガス・水道などのインフラもまとめて整備することができるため、建築コストが抑えられます。よって、賃貸住宅としても家賃を安く設定できるものが多いのが特徴。
テラスハウスは、上下階に他の住戸がないため、子どもが走ったり跳ねたりといった上下階の生活音が気になる人にとっても、より快適に生活できそうです。
ただし、隣家と壁を共有することにより、隣同士の生活音が気になることも・・・。最近では、隣家と接する面に収納を配置している、
遮音性の高い壁を採用しているなど、設計や仕様に工夫のある物件もあります。
テラスハウスは戸建てと比べて断然安い
何故、テラスハウスは、一戸建て住宅よりも価格が安いのでしょうか?
構造上、隣家と共有しているので、建築費を一戸建てと比較をすると安いコストで建築ができます。これに紐付けされるように購入する際も比較的安い価格で購入ができると言えます。
しかし、万が一売却を検討に入れている方であれば、注意が必要です。
テラスハウスは再建築不可のケースや、隣家と切り離しがしたくてもできないという観点から、資産価値が低下することも見込まれます。老朽化をしても建て替えることができないということもあります。
また、住宅ローンで借入の審査される際には、建物や土地の担保評価も審査の基準に加わります。
金融機関は、テラスハウスは再建築不可などのデメリット要素から、万が一の場合債権を回収する事が見込めないと評価されることが多いので、融資をお断りされるケースが多いのも事実です。
すると、ますます買い手がつきづらいことから、価格がかなり安く設定されることが一般的です。
将来、売却を考えている方、資産性を重視している方には、正直向いていないと言えます。
テラスハウスを検討する際には、その辺りを十分念頭に入れて検討しましょう。
~人生に愛すべき住まいを~
さいたま市の不動産の売却・購入は、くさの工務店にご相談ください。
65歳になった知っておきたい3つの価格
2022年08月23日
さいたま市での不動産の売却・購入から居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

新型コロナも落ち着きお盆に帰省をお考えの方も多いと思います。
いよいよ団塊の世代が後期高齢者となる時期に差し掛かり、実家の後始末問題が顕在化しようとしています。
今回は65歳になった知っておきたい3つの価格についてご説明いたします。
※本記事はご両親が健在で、ご両親が戸建ての持ち家に住んでいることを想定しています。
□介護にいくらかかるのか
後期高齢期の住環境の選択肢は「住み続ける」か「移住する」のいずれかです。
多くの方は現状維持である「住み続ける」を選択するのですが、高齢に伴い介護の必要が出てくると破綻してしまう恐れが出てきます。
子供世代が同居しておらず、また、介護が必要になったとしても同居が難しい場合、急いで高齢者向け施設などへの移住を考えなければならなくなるのです。
「住み続ける」か「移住する」かと記載しましたが、実際には「積極的に移住する」か「必要に迫られて移住する」かの選択でしかないのです。
特に高齢になって移住するなんて費用的に難しいと考えている方ほど介護の必要に迫られた時にこれまでの生活が破綻するくらいのダメージを負ってしまいます。
65歳になった知っておきたい3つの価格の1つ目は「介護費用」です。
両親が元気なうちに介護の話を持ち出すのは気乗りしないかもしれませんが、ご両親の意向を踏まえた介護を実現するためには、ご両親が正常に判断できるうちに希望を確認しておく必要があります。
特に実家から離れて暮らしている方は、帰省のタイミングでじっくり話をしておく必要があります。
□住み続けるのにもコストがかかる
65歳になった知っておきたい3つの価格の2つ目は「実家の維持管理コスト」です。
日本人の平均余命は男性が81.64歳、女性が87.74歳(※厚生労働省『令和2年簡易生命表』より)と、65歳から20年以上実家を維持する必要があることがわかります。
雨漏れなどの対策となる屋根・外壁の塗り替え工事は10年~15年間隔で行った方が良いとされます。
10年以上経過すると、キッチンの水栓や給湯器、温水洗浄便座なども故障リスクが高まります。
つまり、今は大丈夫でもそのうち大掛かりなリフォームが必要になるのです。
現在時点で建築士によるインスペクションを実施して、「現状で不具合のある箇所」「耐用年数から交換が必要とされる箇所」「交換が不要な箇所」を区分して、それぞれに必要となる改修費用を算定しておくことをお勧めします。
家は住宅ローンが終わったらおしまい、ではなく、維持管理にまとまった費用がかかることを忘れないようにしましょう。
□資金化できる手段を確保しておく
65歳になった知っておきたい3つの価格の3つ目は「実家はいくらで売れるのか」です。
「介護費用」も「実家の維持管理コスト」も出費ですが、それを補う手段として実家を売る、もしくは貸す、という手段があります。
いざとなったら売ったり貸したりする選択肢を検討しておかないために、例えば多額の「介護費用」が必要になったとしても兄弟・親戚で無理やり費用を工面しているにも関わらず、実家は空き家になっているというような状況が発生してしまいます。
※高齢者施設に入居したから空き家になる家は本当に多いです。
まとまった費用が必要になった時に、実家を売ったり貸したり「資金化」できれば、選択肢を増やすことができます。
ただ、「実家はいくらで売れるのか」を知るためだけに不動産会社に問い合わせはしにくいと思います。
そこで、公示地価などの地価データを探して、ご実家の土地面積を掛けるという方法でおおよその金額を想定することができます。(建物費用を考慮せず土地値だけで判断するのがポイントです)
※ご実家周辺の売り出し情報を見るのもお勧めです。
ご両親がマンションにお住まいの場合はオーナーコネクトもしくはスピードAI査定のご利用がお勧めです。
<オーナーコネクトはこちら>
https://self-in.com/rchukai2/owner
<スピードAI査定はこちら>
https://self-in.com/rchukai2/ai
□一緒に考えるのが重要なポイントです
ご両親の資産や介護の話は、ご両親が元気なうちは話がしにくいものです。
しかし、ご両親の介護の問題はご両親ではなく子供世代が解決するべき課題となります。
万が一の時に判断に必要となる情報は、ご両親が健在なうちに共有してもらうよう、じっくり話し合いをすることをお勧めします。
相続が発生して慌てて駅前の不動産会社に売りに行くのが最悪の状況です。
そうならないために準備を怠らないようにしたいものです。
~人生に愛すべき住まいを~
さいたま市の不動産の売却・購入は、くさの工務店にご相談ください。
住宅性能表示制度とは
2022年08月20日
さいたま市での不動産の売却・購入から居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

住宅購入は決して安い買い物ではありません。食品を買うとには品質を確認して買うのに住宅の品質はなにをみればよいのでしょうか。
住宅には住宅性能表示制度が平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)」に基づく制度です。
住宅品質確保促進法は、住宅性能表示制度や新築住宅の10年保証などについて定めた法律があります。
住宅品質確保促進法は、主に次の3つの制度について定めています。
1.住宅性能表示制度(住宅性能評価)
第三者の専門機関が住宅の性能を評価し、購入者に分かりやすく表示する制度。評価・表示方法は全国共通基準が定められている。なお、住宅性能評価を利用するかどうかは、売主または買主が決める(任意の制度)。
2.住宅専門の紛争処理体制
住宅性能評価を受けた住宅について、引き渡し後に不具合や欠陥が見つかり売主等とトラブルになった場合、「指定住宅紛争処理機関」に紛争処理を依頼できる(手数料1万円)。
3.新築住宅における瑕疵担保期間10年の義務化
「住宅の柱や壁など構造耐力上主要な部分」、「屋根など雨漏りを防ぐ部分」に、瑕疵(工事不備、欠陥など)が見つかった場合について、「引き渡し後10年以内に見つかった場合は、売主(または施工会社など)が無償補修などをしなくてはならない」と定めている。
住宅性能表示のイメージ(新築の場合10分野・中古住宅の場合9分野)
・構造の安定
・火災時の安全
・劣化の軽減
・維持管理更新への配慮
・温熱環境
・空気環境
・光・視環境
・音環境に関すること
・高齢者等への配達
・防犯に関すること
中古住宅では「音環境に関すること」が評価が困難といった理由で、現時点では採用されていないようです。
詳しくは下記を参照ください。
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会HP
新築住宅の住宅性能表示制度ガイド – 国土交通省
いかがでしょうか。文字だけの説明だけだとわかりにくい点もありますが国土交通省や
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページも参考にしてください。
お住まい探しの際に新築・中古住宅の購入の目安になれば幸いです。
~人生に愛すべき住まいを。~
さいたま市の不動産の売却・購入は、くさの工務店にご相談ください。
不動産の所有者の確認方法
2022年08月19日
さいたま市での不動産の売却・購入から居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

戦争などの影響もあり、円安が懸念される情勢ですが、一方で不動産価格の上昇も止まりません。
海外の資産家にとっては、価格の上がった今でも日本の不動産は投資の対象とみられているケースも多いようです。
外国人が不動産を購入した場合の名義
外国人が日本の不動産を購入した場合も、日本人と同様に登記簿にその住所・氏名が記載されます。
ところが、不動産登記法では、登記簿に記載される所有者の住所・氏名に英語を用いることが認められていません(個人の場合)。
そのため、例えば「Michel」さんが購入した場合でも、「ミシェル」や「ミッチェル」または「マイケル」など、任意のカタカナ記載で登記簿に記載することになります。
この場合のカタカナ表記に証明文書などは必要ありませんので、完全に任意の記載になり、法務局での確認はありません。
売主の同一性確認について
そしてこの不動産が売却に出された場合、登記簿に記載された持ち主は「マイケル」さんとなっており、売主として名乗り出た方は、本人確認資料として「Michel」の記載があるパスポートを提出することになります。
この場合、所有者と売主が同一人物であるという確認を取ることは非常に困難です。
もちろん住所氏名以外にも、権利証の提出や、固定資産税の納付状況などから総合的に持ち主であることを判断することになるのですが、一番大切な氏名の一致が取れないという状況は早急な改善が必要だと感じます。
一方で、所有者が会社などの法人の場合には、英語表記が可能となっています。
法人と個人で、表記方法を区別する必要性はあるのでしょうか。
個人についても、英語表記による記録が可能とする議論も必要と感じます。
また、外国人の氏名表記に限らず、日本人でも同姓同名といった場合の混乱もあります。
こうした事態に備え、所有者の情報として「生年月日」を法務局の内部情報として登録する、といった議論もされているようです。
今後はますます外国人の方が国内の不動産を保有するケースは増えていくことが予想されます。
取引の現場がスムーズに行われ、余計なリスクを心配する必要がない制度の設計が待たれますが、同時に、リスクにきちんと目を配ったプロによる目利きが必要となります。
現状のシステムを踏まえたうえで、安全な取引を案内してくれる不動産エージェントと二人三脚による取引を目指しましょう。
~人生に愛すべき住まいを。~
さいたま市の不動産の売却・購入は、くさの工務店にご相談ください。
大雨による河川の氾濫
2022年08月18日
さいたま市での不動産の売却・購入から居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

避難指示の目安となる情報が改善
より早い非難を…
今年は、各地とも異例の速さで梅雨明けとなりましたが、今夏も厳しい暑さとなりそうです。暖かく湿った空気が流れ込むため、局地的な大雨にも注意が必要です。
記録的な大雨によって、西日本は東日本の広い範囲に甚大な被害をもたらした「令和2年7月豪雨」から2年。今年6月から、指定河川について、氾濫水位に達すると予想された段階で譲歩が発表されることになり、より早い段階での避難が可能となりました。
~球磨川流域では、戦後最大の洪水被害の水位を上回った所も~
7月3日から31日にかけて、九州から東北の広い範囲に記録的な大雨をもたらした「令和2年7月豪雨」。期間の総降水量は長野県や高知県の多い所で2,000ミリを超えた所もありました。7月3日から8日は、九州で線状降水帯によって大雨となり、熊本県を流れる球磨川流域では、2カ所の堤防が決壊し、浸水被害や家屋倒壊などの被害が発生しました。
1時間に30ミリを超える激しい雨が約8時間にわたって降り続き、人吉水位観測所では、戦後最大の洪水被害をもたらした時の水位を上回る水位を記録しました。
「令和2年7月豪雨」は、熊本県で非常に大きな被害が発生したことから、「熊本豪雨」ともいわれますが、犠牲者のうち約8割近くが球磨川流域の氾濫による犠牲者と推測されます。
~指定河川洪水予報とは~
気象庁は、国土交通省または都道府県の期間と共同して、あらかじめ指定した河川について、区間を決めて水位または流量を示した洪水の予報を行っています。
これを「指定河川洪水予報」といい、河川の増水や氾濫などに対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるように発表されます。
対象となる河川には、国土交通大臣が指定する河川と、気象庁と協議して都道府県知事が指定する河川があります。前者は、2つ以上の都府県にわたる河川または流域面積の大きい河川で、洪水によって重大な損害が生ずる恐れのある河川です。全国に109水系あり、球磨川はこの中に含まれます。後者はそれ以外の河川で、洪水によって相当の被害が生ずる恐れがあるものです。
~急激な水位上昇に対応し、早い段階で情報を発表~
指定河川降水予報には、氾濫注意情報、氾濫警戒情報、氾濫危険情報、氾濫発生情報の4つがあります。
対象となる河川の水位観測所で、今後予想される流域平均雨量や水位、警戒レベルや警戒すべき事項について記載されています。
今年の6月13日より、指定河川降水予報の氾濫危険情報について、発表の仕方が変更されました。氾濫危険情報とは、自治体が避難指示を発令する目安となる情報です。
これまでは、実況の水位が氾濫危険水位に到達した場合に発表されていましたが、今回、従来の運用に加えて、水位が急激に上昇し、3時間以内に氾濫する可能性のある水位に到達する見通しとなった場合、その予測に基づいて情報を発表できるようになりました。
これにより、これまでより早い段階から警戒を呼び掛けられるため、速やかな避難行動を促すことができます。
大雨で急激に河川の水位が上昇して河川が氾濫すると、いざ避難場所に避難しようとしても避難経路が浸水している場合があります。また、視界が限られるため、夜間の避難も危険です。安全に避難することが難しい場合には、自宅や施設などの少しでも浸水しにくい、高い場所へ移動しましょう。お住まいの地域に、指定河川があるかどうか確認して、大雨の際は、河川の情報も早めに確認しておくと安心です。
購入物件もしっかりと確認しておきましょう。
~人生に愛すべき住まいを。~
さいたま市の不動産の売却・購入は、くさの工務店にご相談ください。
マンション購入の際の「管理費」は適正ですか?!
2022年08月16日
さいたま市での不動産の売却・購入から居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

■「マンションは管理を買う」と言われるぐらい管理は重要です!
マンション購入を検討されている方は、「マンションは管理を買う」というお話を聞いた事がある方も多いのではないでしょうか?一般的にマンションは、人気エリア、駅からの距離、築年数、面積、階高等でその価格相場が決まると言われていますが、もう1つ非常に重要なポイントがあります。それは、マンションの管理状態です。「マンションは管理を買え」と言われるほど、管理状態がマンションの価値を左右してしまうので、注意が必要です。
■マンション管理費が値上がりする理由について
しかし、最近、マンション管理組合が、清掃や修繕費の管理などを担う管理会社から契約更新を拒否されるケースが相次いでいるようです。人件費が高騰する中、管理費の値上げ交渉で折り合いがつかないケースが目立ち、入居者の多くが高齢となった古い物件も少なくなく、次の契約先が見つからなければ住環境が悪化する恐れもあります。その為、不動産購入の際に、不動産会社のスタッフに管理状態の確認や、入居者の世代などをお聞きする事をおススメ致します。
公益財団法人マンション管理センター( https://www.mankan.or.jp/ )には数年前から「管理費の値上げを要求された」「更新を拒まれた」といった管理組合の相談が全国から寄せられているようです。契約辞退の理由として1番多いのが「採算が取れない」といった理由のようです。それも管理会社が値上げを求める理由の一つが人手不足となります。
その理由としては定年が段階的に引き上げられ、13年施行の改正高年齢者雇用安定法で希望者全員が65歳まで働ける仕組みが整ったことで、元の職場で働き続ける人が増え、マンション管理人になる人材が減ったという事だそうです。また、新型コロナウイルスの影響により、外国人労働者が来日できなかったことも人件費高騰につながっている要因とのことです。
■首都圏のマンション管理費はこの10年で18%も上昇した!
2019年の首都圏の新築マンションの管理費は平均1万9085円となり、10年間で18%上昇しているようです。最近の値上げラッシュに、様々な場面でひっ迫している様子が伺えます。
また、契約更新を拒否されることが多いとされるのが、築年数が古く入居者が高齢化した物件のようです。収入を年金に頼る高齢者にとって管理費の値上げは受け入れがたく、交渉が前に進まない事例が目立つようです。また、タワーマンションに住む方で高層階と低層階の住人の意見の違いがあり、トラブルに発展するケースもあるようなので、不動産購入の際には、どのような方が住んでいるかを確認する事は重要です。
管理方法の見直しを進める管理組合も出てきており、最近では「住民経営マンション」というマンション住民が資産価値の維持や住み心地の改善のために意思決定を行って管理・遂行するマンションも増えています。
国土交通省によると、マンションに住む人は2020年末時点で1573万人(推計)。築40年超の物件は20年時点で103万3千戸あり、40年に3.9倍の404万6千戸となる見通しです。2022年4月には改正マンション管理適正化法が施行され、管理組合が機能していないなどの問題があるマンションの管理について自治体が助言、指導できるようになりました。
名古屋市は条例で、2022年度に管理組合に運営状況などの届け出を義務付ける方針となっており、管理組合が機能していない場合はマンション管理士を派遣するなどして助言、指導を進める予定との事です。このような動きは自治体によって増えていく事が予想されます。
不動産購入時にマンションを検討される方は「管理費」にも必ず注目してもらいたいと思います。
今後の参考にお役立て下さい。
~人生に愛すべき住まいを。~
さいたま市の不動産の売却・購入は、くさの工務店にご相談ください。
売る時に価値が下がりやすい物件とは?(嫌悪施設編)
2022年08月09日
さいたま市での不動産の売却・購入から居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

どんな物件を購入すると、そのご資産価値が下がりやすい可能性があるのでしょうか。
本日は、その第2弾で、嫌悪施設の近くにあったり、お部屋から見える物件です。
資産価値を下げてしまう可能性のある嫌悪施設とは、主に、墓地、火葬場、高圧線鉄塔、ごみ焼却場、ガスタンク、悪臭・騒音・振動等を発生させたり危険物を取り扱う工場、暴力団事務所、悪臭を発する川、火薬類貯蔵所、大気汚染や土壌汚染の原因となる施設等や住宅地としての風紀が乱れる施設をさします。
また、大型車両の出入りが多かったり、騒音を伴う荷物の積み下ろしが多い倉庫なども嫌悪施設の一つとなり得る場合があります。
不動産会社の営業マンは、「このような嫌悪施設に隣接する物件は価格が安いので、自分達が気にならなければ、逆にお買い得物件です」などとアドバイスする場合もありますが、自分たちは良くても、次に買う方や借りる方が気にする場合があるため、資産価値が下がってしまう可能性はあります。その辺りは注意して購入を検討しましょう。
【追伸】
墓地については、嫌悪施設の一つと言われており、デメリットに思う方も多いかもしれませんが、お墓に近い家は実はメリットもありますので、その辺りも考慮しておきましょう。
墓地が近くにある物件の主なメリットは以下の6つ
- 住環境は基本的に変わらない
- 日当たり・風通しが良い
- 閑静で自然が豊かなケースが多い
- 地盤が良いケースが多い
- 家賃が割安な物件が多い
- 市場価格よりも安く設定されていることが多い
超都心でもお寺などはたくさんあります。墓地が近くにあるから必ずしも資産価値が下がるという訳ではありません。不動産は一長一短ありますので、総合的に判断していくことをお勧めします!
~人生に愛すべき住まいを。~
さいたま市の不動産の売却・購入は、くさの工務店にご相談ください。
2022年8月 フラット35金利のご案内
2022年08月08日
さいたま市での不動産の売却・購入から居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

2022年8月のフラット35金利は、20年以下が1.20%、21年以上が1.33%と前月から0.02%引き上げとなりました。 大手都市銀行の動向については、固定期間10年の最優遇金利について、三菱UFJ銀行が先月から-0.05%、三井住友銀行が先月から-0.06%、みずほ銀行が先月から-0.10%とそれぞれ引き下げとなりました。 今年に入り上昇基調だった長期金利が日銀による強力な金融緩和により上限が抑えられていることなどが影響しているとみられています。
【フラット35 8月実行金利】
借入期間15年~20年 1.20%(前月+0.02%) 借入期間21年~35年 1.33%(前月+0.02%) ※上記金利には団信特約料が含まれておりません。
フラット35の制度変更が行われます
2022年度の予算が成立し、2022年4月よりフラット35の制度改正が行われます。
2022年度4月以降の制度変更事項
【フラット35】維持保全型がはじまりました
2022年4月適合証明書交付分から、維持保全・維持管理に配慮した住宅や既存住宅の流通に資する住宅を取得する場合、【フラット35】の借入金利が当初5年間年0.25%引き下げとなりました。
【フラット35】地域連携型(子育て支援)の金利引下げ期間が拡大されました
2022年4月資金実行分から、住宅金融支援機構と連携している地方公共団体の子育て支援のための補助事業の利用とあわせて、【フラット35】の借入金利が当初10年間年0.25%引き下げとなりました。
誰だって間違える
2022年08月06日
さいたま市での不動産の売却・購入から居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

不動産登記簿を見ていると、たまに「更正」という文字が記載されていることがあります。
一方で「職権更正」という記載もありました。
この違いは何でしょうか。
申請者の間違いによる「更正」
まず「更正」ですが、これは登記を申請した人間のミスになります。
自分で申請した場合も、専門家に依頼した場合も同じく、申請書に記載された情報が間違っており、そのまま登記がされてしまい、後日その間違いが発覚したケースです。
申請書に誤った住所を記載してしまった、名前の漢字を間違えてしまった(例:「渡邊」と「渡邉」)、日付を間違えてしまった、などのケースです。
大抵のケースでは、添付した書類との整合性がとれず、登記がストップされるのですが、場合によってはそのまま記録されて登記が出来上がってしまうケースもあります。
この場合には、改めて「更正」の申請書を提出して、正しい情報に書き換える必要があります。
法務局の登記官の間違いによる「職権更正」
一方で、申請した人間の間違いではなく、登記記録を入力した登記官の間違いによる場合もあります。
申請書には正しい情報が記載されていたのに、登記官が見落とした場合などです。
また、以前の古い簿冊の登記簿から、現在のコンピュータ情報へ打ち直す際に、登記官が誤って入力してしまっている場合もあります。
この場合には、登記官が「職権」により更正登記を行います。
どちらも、更正により正しい情報へ書き換えることが可能ですが、登記記録上は「更正」や「職権更正」といった記録が生じてしまい、間違いが起こったことが明示されてしまいます。
実害がないとはいえ、できればそのようなミスがない登記簿が好ましいでしょうか。
普段は細かく見ない不動産の登記簿ですが、中には重要な情報やリスクに関する記載がある場合もあります。
~人生に愛すべき住まいを~
さいたま市の不動産の売却・購入は、くさの工務店にご相談ください。
大雨の時期だからこそ見直したい 住宅購入検討時のハザードマップの重要性
2022年08月05日
さいたま市での不動産の売却・購入から居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

梅雨らしい天候がないまま梅雨明けした途端に日本全国で大雨被害が警戒される嫌な天気が続きました。
気候変動などの影響からゲリラ豪雨と呼ばれる大雨被害が毎年のように報道されるようになり、各地で土砂災害も発生しています。
自然災害への備えは、「災害に見舞われないなら意味がない」と、対策の実施に後ろ向きな方が多いのですが、「天災だから致し方ない」と思えるのは十分に準備を行っても被害にあった場合だけで、「あの時こうしておけば…」とその後の人生に大きな傷を残してしまう結果になりがちです。
今回は大雨の時期だからこそ見直したいハザードマップについてご説明いたします。
■住み替えは最大の防災対策です
土砂災害、洪水、地震、噴火など日本は災害大国です。
絶対に安全と言い切れる街はほとんどなく、日本に住む以上、自然災害への備えは必要です。
数年前、大規模な土砂災害が発生した時に、その地域から住み替えることが防災対策だ、という発言をして批判を受けた元政治家の方がいらっしゃいましたが、災害からの復旧のコストや災害で失われる財産などを考慮すると、「その街に住まない」は効果の高い対策と言えます。
※被災された方に対する配慮のない発言で非難されるのは仕方がないのですが、平常時ならば当たり前のことを言っているに過ぎません。
既に家を所有してしまっている場合、住み替えを実現するなら、自宅を売却し、更に現在の予算の範囲で購入する(賃貸に移るという選択もあります)という労力も金銭的な負担も大きな対策となってしまいます。
住み慣れた街を離れなければならないという心理的負担も大きいです。
一旦家を所有してしまうと、防災対策のために住み替えるのは現実的とは言えません。
しかし、これから家を購入する場合は別です。
災害リスクを十分に検討した上で、よりリスクが少ない街を選ぶことはそれほど難しいわけではないのです。
■気に入った物件が見つかったら必ずハザードマップを確認しましょう
不動産購入の際には検討しなければならないことがたくさんあります。
希望条件が絞られてきて、エリアの予算感がぼんやり身に付き始めると、月々のローン返済額や物件以外の諸経費など現実的なお金の問題に直面します。
お金の問題と、将来被害にあうかどうかわからない災害リスクを天秤にかけてしまうと、どうしてもお金の問題を優先しがちです。
例えば希望エリアではどうしても予算オーバーになってしまう場合で、土砂災害警戒区域内だけれども手が届く割安な物件がでたらどうでしょう?
実際には「掘り出し物」と言われる物件を一般の消費者が購入するのは難しいです。つまり割安物件は相応の理由がある訳ですが、現実的な価格を見てしまうと、「被害にあうかどうかもわからないし…」と災害リスクから目を背けてしまうのが人情です。
ハザードマップを確認して災害リスクの高いエリアを避けることや、耐震性が確保された住宅を選択することは、住宅購入における検討事項ではなく、住宅購入における必須条件です。
義務化されていないからなど理由を付けて災害リスクから目を背けてしまうと、本当に被災してしまった場合、特にご家族に被害が出てしまった場合に、取り返しのつかない大きな傷を残してしまうことになります。
住宅購入は災害リスクを軽減するチャンスです。
ある程度エリアが絞られてきたら、あるいは気になる物件が見つかったら、かならずハザードマップを確認しましょう。
■災害リスクに備えた生活を作る
一口に災害リスクと言っても土砂災害、洪水、地震、津波、噴火など様々です。
冒頭にも申し上げた通り、日本は災害大国なので、災害リスクを完全に取り除くことは不可能です。
ご家庭の事情やお仕事の関係で、洪水が懸念される地域を選ばざるを得ない場合もありますし、地震被害を恐れるあまり、多額の費用をかけて過剰に耐震性を向上するのも間違っています。
また、災害を恐れるがあまり、予算オーバーの物件に手を出して、購入後の生活に支障が出るのも間違っています。
現実的なお金の問題を考慮しつつ、どこまで妥協できるかを突き詰めるのが、不動産購入に際に行うべき重要なプロセスです。
仮に津波が警戒されるエリアの物件を購入したとします。
建物で津波を防ぐことはできないので、津波警戒エリアに住む人は、津波警報が発令されたら高台へ素早く避難しなければなりません。
家財が失われることより命が助かることの方が大事だからです。
ご存じのように津波警報が発令されても大きな被害に至ることはあまりありません。
それでも警戒エリアに住む人は避難を続けなければなりません。
100回空振りでも101回目で助かった…、それが東日本大震災で実際に起きたことです。
住むエリアのハザードマップを確認し、想定される災害規模を把握し、家にいることで防げないリスクを抱える場合は、安全を確保する方法を確認しておくことが大切です。
家は幸せの象徴であり、家族を守る砦であるべき、ということをいま一度思い出して、万が一に備える住宅購入を実現したいものです。
~人生に愛すべき住まいを~
さいたま市の不動産の売却・購入は、くさの工務店にご相談ください。
災害に備えた家づくり
2022年08月03日
さいたま市での不動産の売却・購入から居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。
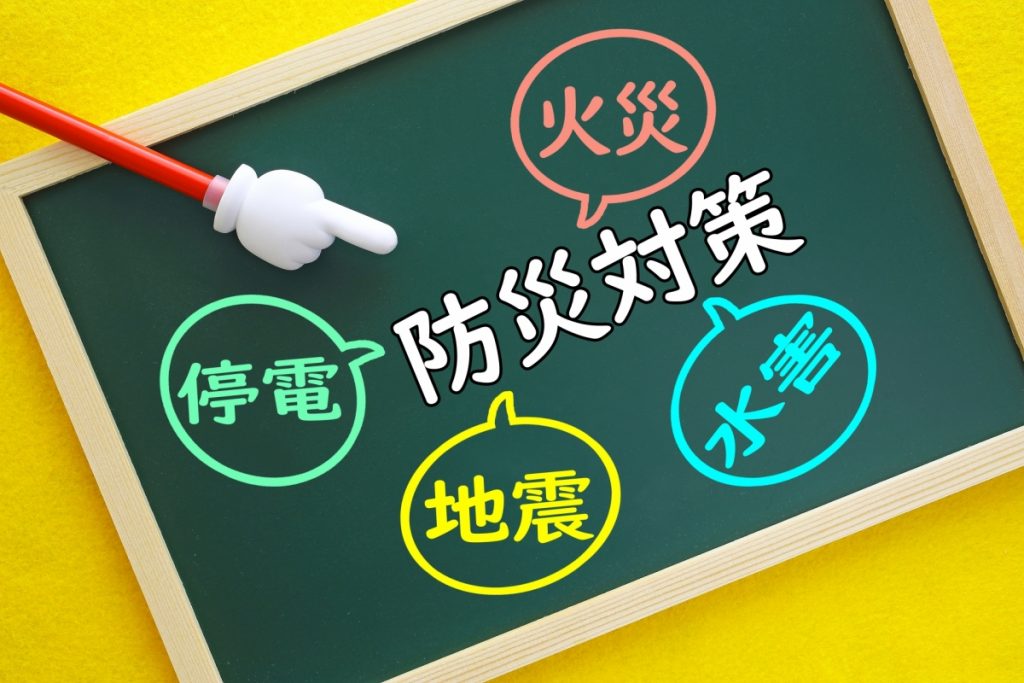
まず簡単にできる事から
これから購入の検討中の場合
保険の見直し
~人生に愛すべき住まいを~
さいたま市の不動産の売却・購入は、くさの工務店にご相談ください。
米国のShelter in placeを取り入れた新しい避難枠組み「避難所2.0」へのアプローチ
2022年08月01日
さいたま市での不動産の売却・購入から居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

災害発生時に避難所に避難する、という従来型の避難戦略は、避難所設置余地の少ない都市部への人口集中や避難の難しい高齢者の増加、感染症対策のための安全距離の確保による避難所収容力の低下などを背景に、限界を示しつつあります。
この課題へのソリューションとして注目されているのが、自宅に留まり安全に避難する“Shelter in place”という米国の考え方です。日本でも、避難所まで移動する「水平避難」に対して、その場に留まる「待避」や建物の上層階に登る「垂直避難」を状況に応じて使い分ける考え方が一般化しつつありますが、”Shelter in place”はさらに一歩進んで、自宅避難を想定してあらかじめ災害に強い家を作り、災害時の自宅避難の可能性を能動的に高めていく動きです。
今回はShelter in placeという概念を取り入れた新しい災害時避難の枠組みを「避難所2.0」と呼び、それを推進する動きとして、立地選択や建物建築に対するインセンティブの強化、中でも重要な取組みとして、災害に強い家に「認証」を与える方向性について考察します。
新しい避難の枠組み実現のための要件
先に触れた新しい避難の枠組み、「避難所2.0」を実現するためには、制度面を整備することにとどまらず、人々の意識を変え、行動変容を起こすためのソフト面からのアプローチが重要になってきます。
災害発生前には「人々が災害に強い家を建てること(立地・構造要件)」が、災害発生時には、「状況に応じて最適な避難行動をとること(最適行動選択要件)」が求められます。
建物の構造・立地要件としては、災害リスクの低い土地に家を建て、災害が発生してもそれに耐える構造の家を建てることが求められます。しかし、過去に被災した土地や災害への備えが弱い家は、初期の購入コストが低いため、災害に弱い土地に災害に弱い家を建てることにメリットが生じてしまいます。
これを修正するためには、行政等が意図的に介入することも必要となります。例えば、国土交通省では、2021年5月の改正法公布を受け、「長期優良認定制度の見直しに関する検討会」を設置し、災害配慮の考えを含む長期優良認定制度の新基準について議論を重ねました。これにより、2022年2月より認定基準に「自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること」が追加され、災害の危険性が時に高い区域を認定対象から除外し、災害リスクが高い区域では、必要な措置を求めることができるようになりました。
【長期優良認定制度における災害配慮の基準】
○認定を行わないことを基本とする区域の例
- 土砂災害特別警戒区域
- 地すべり防止区域
- 急傾斜地崩壊危険区域
○認定を行わない、または、認定に当たり必要な措置を求めることができる区域の例
- 浸水被害防止区域
- 災害危険区域
- 津波災害特別警戒区域
○認定に当たり必要な措置を求めることができる区域の例
- 津波災害警戒区域
- 土砂災害警戒区域
- 洪水浸水想定区域
- 雨水出水浸水想定区域
- 高潮浸水想定区域
また、行政が今後このような「避難所2.0」の考え方をとりいれ、人々に対して、災害時には避難所への移動だけでなく自宅に留まる選択肢もありうるという立場を強調するようになれば、逆に、どんな災害が起こってもどんな家に住んでいても、自宅に留まろうとする傾向がこれまでよりさらに強まるでしょう。
そのため、「避難所2.0」の時代における災害時リスクコミュニケーションは、従来同様あるいはそれ以上に、自宅に留まっては危険な人に対して「避難所に避難してください」というメッセージを伝えることが重要になるものと考えられます。それによって、垂直避難と水平避難を有効に使い分ける「最適行動選択要件」が満たされることになるでしょう。
これら「避難所2.0」の取組みにより、安全な場所に安全な構造の家が数多く建つことにより地域全体の防災力が底上げされ、公的な防災コストの削減につながると考えられます。さらに、災害時には安全な家に住む人々に的確に自宅待機を選択してもらうことで、避難所のキャパシティや維持コストをコントロールしつつ、自宅に留まった人々・避難所に移動した人々、双方の被災者のQOL(生活の質)を高めていくことが可能となります。
まずは、災害に弱いエリア・住宅の選択をしないよう、住宅購入時には確認が必要となるかと思いますので、ご自身での確認も勿論ですが、その辺りも助言してくれるエージェントを探す方がより安全な住宅選びにつながるかと思います。
~人生に愛すべき住まいを~
さいたま市の不動産の売却・購入は、くさの工務店にご相談ください。
最近の投稿
アーカイブ
- 2023年6月 (12)
- 2023年5月 (26)
- 2023年4月 (12)
- 2023年3月 (28)
- 2023年2月 (6)
- 2023年1月 (24)
- 2022年12月 (19)
- 2022年11月 (19)
- 2022年10月 (21)
- 2022年9月 (17)
- 2022年8月 (16)
- 2022年7月 (20)
- 2022年6月 (22)
- 2022年5月 (20)
- 2022年4月 (25)
- 2022年3月 (10)
- 2022年2月 (19)
- 2022年1月 (18)
- 2021年12月 (19)
- 2021年11月 (21)
- 2021年10月 (22)
- 2021年9月 (21)
- 2021年8月 (16)
- 2021年7月 (22)
- 2021年6月 (26)
- 2021年5月 (21)
- 2021年4月 (22)
- 2021年3月 (30)
- 2021年2月 (29)
- 2021年1月 (23)
- 2020年12月 (13)
- 2020年11月 (23)
- 2020年10月 (23)
- 2020年9月 (15)
- 2020年8月 (19)
- 2020年7月 (16)
- 2020年6月 (27)
- 2020年5月 (21)
- 2020年4月 (17)
- 2020年3月 (16)
- 2020年2月 (18)
- 2020年1月 (21)
- 2019年12月 (10)
- 2019年11月 (20)
- 2019年10月 (16)
- 2019年9月 (21)
- 2019年8月 (13)
- 2019年7月 (28)
- 2019年6月 (35)
- 2019年5月 (30)
- 2019年4月 (15)
- 2019年3月 (38)
- 2019年2月 (32)
- 2019年1月 (31)
- 2018年12月 (2)
- 2018年11月 (11)
- 2018年10月 (8)
- 2018年9月 (19)
- 2018年8月 (19)
- 2018年7月 (35)
- 2018年6月 (14)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (7)
- 2018年3月 (3)
- 2018年2月 (32)
- 2018年1月 (29)
- 2017年12月 (27)
- 2017年11月 (25)
- 2017年10月 (22)
- 2017年9月 (13)
- 2017年8月 (33)
- 2017年7月 (38)
- 2017年6月 (19)
- 2017年5月 (22)
- 2017年4月 (25)
- 2017年3月 (9)
- 2017年2月 (13)
- 2017年1月 (15)
- 2016年12月 (20)
- 2016年11月 (29)
- 2016年10月 (18)
- 2016年9月 (27)
- 2016年8月 (16)
- 2016年7月 (23)
- 2016年6月 (25)
- 2016年5月 (27)
- 2016年4月 (29)
- 2016年3月 (23)
- 2016年2月 (13)
- 2016年1月 (22)
- 2015年12月 (11)
- 2015年11月 (18)
- 2015年10月 (24)
- 2015年9月 (5)
- 2015年8月 (5)
- 2015年7月 (2)
- 2015年6月 (3)
- 2015年5月 (2)
- 2015年4月 (4)
- 2015年3月 (8)
- 2015年2月 (8)
- 2015年1月 (6)
- 2014年12月 (1)
- 201年11月 (1)
カテゴリー
- お金・住宅ローン・税金 (112)
- くさの工務店の新築工事 (25)
- コラム (104)
- ご案内 (19)
- 不動産・トラブル (64)
- 不動産取引ガイド (1,394)
- 動画 (22)
- 売却 (17)
- 改修工事・リフォーム工事 (32)
- 未分類 (20)
- 物件紹介 (80)
- 生活 (25)
- 相続・贈与 (33)
- 空地空家 (57)
- 購入 (99)